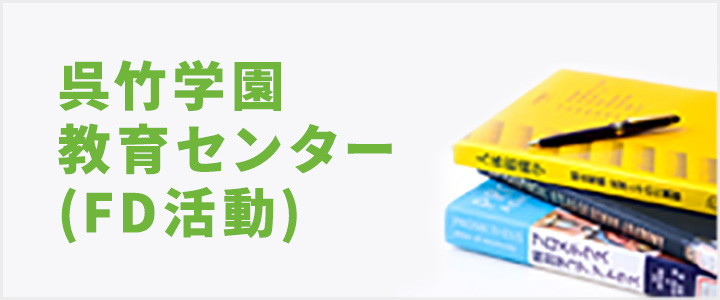鍼灸科附属施術所について
鍼灸科附属施術所は地域医療への貢献のため他の養成校に先駆け1979年に開設しました。その後、1985年に「卒後臨床研修」を開始、1990年に「卒前教育プログラム」として当施術所での臨床実習がカリキュラムに導入されました。
1995年には全国のはり師・きゅう師養成校にモデル校として「(卒前)ベッドサイド実習」を開始しています。
長い歴史の中で、日本でのはりきゅうは自然医学と現代医学が融合し、さらに日本人の体質に合わせて発展した医療技術です。そして、日本人の体質に合わせたマイルドな日本のはりきゅうは、現代人の身体症状にも適した施術方法と考えています。
当施術所は創立以来、臨床教育に力を入れ、はりきゅう施術を用いた医療貢献と、はり師・きゅう師の人材育成に尽力しています。
日常におけるお困りの症状等がございましたらご相談ください。



はりきゅう施術を希望される方へ
■所在地
〒160-0008
東京都新宿区四谷三栄町16-12
東京呉竹医療専門学校1号館1階
四ツ谷駅から徒歩4分
■予約時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:40〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:10〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13:50〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15:20〜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18:30〜 | ○ | ○ | ○ (2025年 4月から) |
||
| 専門外来 (午前のみ) |
女性外来 小児外来 緩和外来 |
休日:土曜日、日曜日、祝日、学校の休日
*事前予約制となっております。まずはお電話にてお問い合わせください。(お電話受付時間:平日9:30~18:00)
TEL:03-3357-7328
(お問い合わせ、ご予約はお電話にてお願いいたします。)
*原則、担当指名制はお受けしておりません。
*施術時間は1回60分前後です。
*女性外来:女性特有の症状についてご相談ください。
※症状や疾患によっては、医療機関の受診をご提案させていただく場合もあります。
*緩和外来:提携医療機関からの紹介のもと、緩和医療領域の諸症状に向き合っています。
※提携医療機関からの紹介のみとなります。
*小児外来:0~12歳(小学生)までを対象としています。お子さんの諸症状についてご相談ください。
ご相談の多い症状は、下痢や便秘、夜泣き、食欲不振など。
■料金
| 種別 | 一般 | 町内※2 | 小児※3 |
|---|---|---|---|
| 通常時 | 2,000円 | 1,500円 | 500円 |
| 臨床実習協力時※1 | 1,000円 | 1,000円 | |
| 療養費※4 | 初回:400円〜1,000円程度 2回目以降:200〜500円程度 |
||
- ※全ての種別において、有資格研修生による施術や学生の臨床実習にご協力をいただく事を
ご理解いただいております。 - ※1学生による臨床実習のご協力をいただいた際の施術費です。
- ※2町内割引対象地域:四谷三栄町在住の方および四谷二丁目在住の方が対象です。
- ※30~12歳(小学生)までを対象としております。ご相談の多い症状は、下痢や便秘、夜泣き、食欲不振など。
- ※4健康保険負担割合により、窓口でお支払いいただく費用が変わります。
かかりつけ医より同意書の発行をいただきます。かかりつけ医がいない場合、担当者へご相談ください。 - ※その他、本校の卒業生や学生は別途の施術費を設けています。
■備考
- ・鍼(はり)と灸(きゅう)の臨床施設です。
- ・指導鍼灸師や教職員に加え、有資格研修生が担当します。
- ・学生による臨床実習期間の際は、実習へのご協力を相談させていただきます。
※教員とともに、1年生は見学、2年生は医療面接(問診)や検査、3年生は医療面接や検査、施術を行います。 - ・療養費(医療保険)の適用が可能です。
※但し、かかりつけ医の同意と6か月に1度の再同意(受診)が必要です。かかりつけ医がいらっしゃらない場合、ご相談ください。
■当施術所の特徴
- ・ 公益社団法人全日本鍼灸学会*指定研修施設
- ・ 同 指導鍼灸師・認定鍼灸師 在籍
- ・ 国民のための鍼灸医療推進機構(AcuPOPJ)*指定研修施設
- ・ 同 認定指導員・研修修了者在籍
- ※公益社団法人全日本鍼灸学会とは→唯一の日本における公の鍼灸関連学会です。
- ※国民のための鍼灸医療推進機構とは→現代日本鍼灸界をリードする4つの団体が設立した任意団体です。
- ・上級救命技能認定者在籍(公益財団法人 東京防災救急協会)
- ・赤十字ファーストエイドプロバイダー(赤十字救急法救急員)在籍(日本赤十字社)
- ・BLS(1次救命処置)プロバイダー在籍(アメリカ心臓協会:AHA)
■医療連携
以下の施設と連携を図り、患者さまの心身の貢献を図っています。
- ・ 埼玉医科大学 東洋医学科
- ・ 国立がん研究センター中央病院 緩和医療科
- ・ 社会福祉法人 三井記念病院 総合内科
- ・ 筑波技術大学保健科学部附属東西医学統合医療センター
- ・APネットワーク(鍼灸と精神医療の相互ネットワーク:昭和大学発達障害医療研究所 中村元昭准教授)田中内科医院 など
卒前臨床教育・卒後臨床研修制度
■鍼灸科附属施術所の設置目的・理念
地域社会や地域医療に貢献すると共に、はり師・きゅう師としての基本的臨床能力を備え、他(多)職種連携の中で医療実践が出来る人材育成を目的とする。
また、医療者として常に研鑽し、その姿勢を後進に示す先導者の育成を目的とする。
鍼灸科附属施術所 所長 藤田洋輔
■卒前臨床教育(臨床実習)
早期より参加型臨床実習を行い、はり師・きゅう師における医療人としての意識の涵養と臨床像の展望を図っています。そのため、教員・指導鍼灸師の指導のもと、1年生の実習では見学、2年生では医療面接(問診)および検査、3年生では更に施術を加え実習を行っています。これらの臨床教育により、より実践を意識した医療人育成を目指します。
■卒後臨床研修
卒後間もない時期に臨床における自律性を高め、偏りのない臨床を経験し研鑽することは、はり師・きゅう師として、さらには医療人として重要なことといえます。卒業して臨床の場に立つと「もっと勉強しなければ」と痛感することもあるでしょう。そんな時の糧となるのが卒後臨床研修制度です。臨床の場で堅実に実践できるように指導しています。
*研修生の研鑽内容
狭義の臨床技術(触察、はり施術・きゅう施術・衛生的操作など)に加え、傾聴やコミュニケーションによる患者さんへの寄り添いや向き合い、病態を推論するための各種検査法、それらを基にした病態の推察能力、導き出した病態に対しリスクに気づく視点や(はりきゅう)専門職としての最大限の貢献、これらをはり師・きゅう師が身につけ実践すべき基本的な臨床能力と考え、日々研鑽しています。
■備考
その他、卒後臨床研修では、はりきゅう臨床から得た経験を、指導鍼灸師とともに学会などの対外的な報告を行い、はりきゅうや医療の発展に貢献しています。